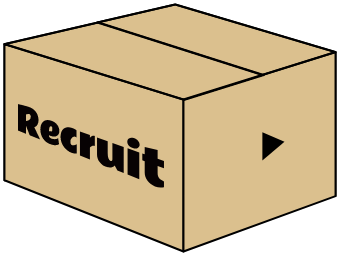COLUMN コラム
連載コラムVol.7 SDGs

先日、TEAM NACSの森崎博之氏脚本・演出作品「HONOR」を観劇する機会に恵まれた。多様な価値観が渦巻く時代の変遷の中で,普遍の価値、喪失と再生、未来の構築に切り込んだ作品と私なりに感じた。失われた森を己の信念に基づき植林して再生させるくだりは,サスティナブルな社会の構築を感じさせる。
「サスティナブル~持続可能な社会の構築」、SDGsの流れである。SDGs活動、社会活動のトレンドで現在の企業経営では重要な要素と心得る。この作品を18年前に創作したことは先見の明である。
弊社は現在、将来を見据え企業として持続可能性を高めるためSDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいる。刻々と変化する現代社会において、どのようにして企業価値を高めるか、鋭意努力しているところである。そのアクションプランを近々皆様にお示しできるのではないかと思います。
このSDGsの流れ、昨今、巷で積極的に取り組んでいる状況ですが、発想や思想的な概念は古くから存在していたように感じられ、文学作品の中でもその一端を垣間見ることができる。
今から90年以上前に発表されたある童話がある。「虔十公園林」(けんじゅうこうえんりん)宮沢賢治の作品である。私と同世代の方であれば、小学6年生の国語の教科書に載っていたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれない。
物語は、虔十という知的障害の少年が、痩せた土地に杉の苗を植えて、周りからどんなに馬鹿にされても、からかわれても何時も笑いながら杉を育てる。そして、そこが子供たちの遊び場になり、その子供たちが成長して偉人となり、最終的にその地域に大きな貢献をもたらし、彼らの故郷であり続けるサスティナブルなお話。まさに持続可能な社会の構築~SDGsなのである。
先入観や常識にとらわれずに将来を見据えて何をすべきか、出来ない理由ではなく、するための方法を考えることが大切なのではないか。「虔十公園林」では達成された持続可能な開発目標の世界が描かれている。弊社の目標(アクションプラン)が達成された未来は見えないが、「虔十公園林」を一読して参考にしてはどうか?
この記事を書いた人
専務取締役田村 智樹