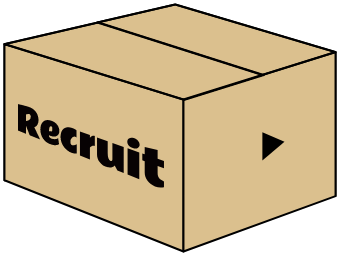COLUMN コラム
連載コラムVol.6 幸せと油揚げ

今夏の猛暑も去り、爽やかな秋風を期待していますが、残暑厳しい今日この頃です。皆様、如何お過ごしですか。私たち技術者の夏と言えば、「技術士二次試験(筆記)」を乗り越えるのが恒例行事となっています。何せ技術士資格を取得し国家からお墨付きを頂くための重要な試験ですから、試験を終え安堵している方も多いのではないかと思います。
この試験の必須問題で、わが国の建設行政について問う問題があります。その解答の常套句として、「わが国は戦後、目覚ましい経済発展を遂げ、世界第4位の経済大国になった。」という書き出しがあります。このセンテンスに続き建設行政に係る現状の課題を抽出し解決策を示すのが解答形式となります。因みに私が受験した24年前は世界第2位でしたが…
このように、わが国のGDPは世界第4位に後退しましたが、まだまだ上位に位置する経済大国です。しかし、何故かその実感が湧かないのも私たちが直面する課題ではないでしょうか。この特異な現象を裏付ける例として幸福度の視点でわが国を見てみると、毎年50位前後で推移している事実が挙げられます。即ち、豊かさと幸福度が比例しないのです。
この構図を日本国内、都道府県単位で着目してみたらどうなるのか。都道府県単位のGDPは、上位より東京都、大阪府、愛知県、神奈川県と続き、わが北海道は第8位程度で推移しています。幸福度(一般財団法人日本総合研究所)は、上位より福井県、石川県、東京都、富山県と続き、わが北海道は40位前後の下位低迷状態です。注目すべきは幸福度の上位が北陸3県で独占されていることです。この3県のGDP順位は30~40位程度で、この結果からも東京都は例外として世界規模と同様に豊かさと幸福度が比例しない傾向を示します。
では、何故このようなことになるのか。この疑問は、あるお寺で開催された法話に中で解決しました。法話を行った僧侶が明瞭簡潔に回答したのである。曰く「油揚げを食べるからだ!」即ち、油揚げの消費量と幸福度は比例するのである。
福井県は油揚げの消費量が日本一で、かつ浄土真宗の信仰が篤い仏教王国。したがって、報恩講をはじめとする仏事や法要などを背景としたお斎(おとき)という食文化が伝統的に根付いている。石川県、富山県も同様の傾向を示し、その歴史は700年以上にも及ぶ。お斎とは、仏事や法要の後にもてなされる会食のことで、精進料理が振る舞われ、その中で貴重なたんぱく質として油揚げが好んで食されてきた。
篤い信仰心が故に人々が集い油揚げを食べる。信仰と食の相互作用で満足感、高揚感が得られ人々は笑顔になる。そこでは会話が弾み、そしてコミュニティーが形成され、相互扶助の精神が生まれる。人と触れ合うこと、支え合い助け合うことで幸せを感じる。食文化は人々を幸せにするのである。福井県、石川県、富山県の幸福度が高いのは、篤い信仰心を介して形成された食文化が一因として考えられる。
北海道の幸福度は残念ながら下位低迷である。しかし、北海道にはわが国の食糧基地として豊かな食材を有する強みがあります。この強みを生かすことで幸福度を上昇させることも可能ではないのか。北陸の歴史的な食文化に習い、ある要素を介して刺激することで豊かな食材を生かした食文化を形成し、そこに幸せが生まれるのではないか。
昨年、「食」と「映画」を軸にした北海道発の祭典が開催され成功裏に終わっている。今年も10月に開催される予定である。映画というコンテンツを介して食文化を形成し、そこに人々が集う。人々が集えば支え合い助け合う。相互作用で満足感、高揚感で得られる・幸せを感じる。即ち、幸せは映画を見て食べ歩くことで得られるのである。
このように「食と映画」という北海道独自の文化により持続可能な社会が形成されれば北海道の未来は明るいのではないか。この祭典が北海道の幸福度上昇の起爆剤になるのではないかと期待したい。
北海道において食と映画は幸せであり、幸せは支合わせである。
この記事を書いた人
専務取締役田村 智樹