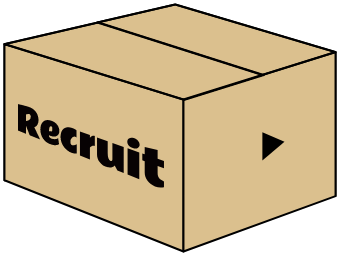COLUMN コラム
屯田兵の血を引く技術者として

先人の足跡を辿る
私の曾祖父・小川注連吉(おがわ しめきち)は明治時代に北海道へ渡った屯田兵の一人でした。彼が汗と涙で開墾した大地に、私は橋梁エンジニアとして新たな歴史を刻んでいます。土木技術者として、先祖が切り拓いた同じ土地に橋を架けるという不思議な縁を感じずにはいられません。
屯田兵としての小川注連吉
曾祖父は明治時代、政府の屯田兵募集に応じて家族と共に北海道へ渡りました。当時の屯田兵は「軍人であり農民である」という二重の役割を担い、未開の大地と向き合いました。彼らの世代がなければ、今日の北海道の発展はなかったでしょう。
厳しい開拓生活
北海道の厳冬は本州出身の曾祖父一家にとって想像を絶するものでした。マイナス30度を下回る気温、一晩で家を埋め尽くす雪、そして短い農耕期間。家族の言い伝えによれば、最初の冬は「朝起きると布団に霜が降りていた」そうです。原生林を切り開き、巨大な切り株を抜き、石ころだらけの土地を耕す日々。多くの入植者が病気や過労で倒れる中、曾祖父は家族を支え続けました。
開墾地に架ける橋
時は流れ、曾祖父が命を懸けて開墾した土地は今や北海道の重要な交通路となっています。私は土木コンサルタントとして、その地に新しい橋梁を設計する機会に恵まれました。設計図を引きながら、かつてこの地で曾祖父が鍬を振るった姿を想像します。彼が見た原生林の風景と、今の発展した街並み。その変化の中に、日本の近代化の歴史を感じずにはいられません。
技術の継承と進化
曾祖父が使った道具は鍬とスコップ、そして自らの筋肉でした。私はコンピュータを駆使して橋を設計しました。道具は変われど、自然と向き合い、人々の暮らしを支えるという本質は変わりません。
設計した橋には最新の耐震技術を採用しました。北海道の厳しい気候に耐え、次の世代まで安全に使い続けられる構造物を目指しています。
受け継がれるフロンティアスピリット
屯田兵だった曾祖父から技術者の私へ、直接の技術継承はありませんが、「困難に立ち向かう精神」は確かに血として受け継がれています。
橋の完成時、空を見上げたとき、曾祖父もどこかで見守ってくれているような気がしました。開拓者の血を引く技術者として、これからも北海道の発展に貢献していきたいと思います。
この記事を書いた人
常務取締役小川 達也